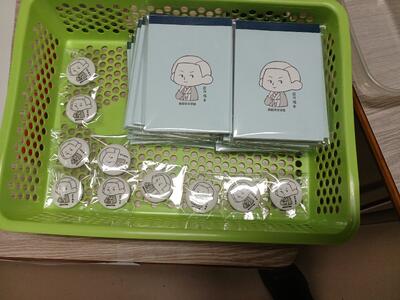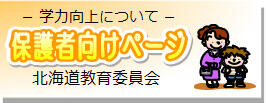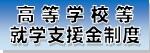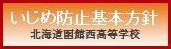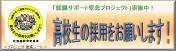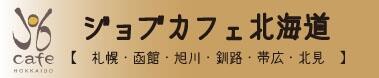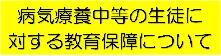学校行事などをお知らせします
令和7年度PTA交通安全街頭指導を実施しました
7月16日(水)、今年度のPTA交通安全街頭指導を実施しました。PTAの皆さんと本校教員合わせて約20名が、本校生徒の多くが通学で利用する八幡坂、日和坂、末広町電停などにて、下校時の安全を見守りながら、通学マナー向上に向けて声かけを行いました。また、今回も函館西警察署による自転車交通マナー向上を呼びかける取り組みも合同で行われました。
朝から降った雨の影響があり、大変蒸し暑い時間帯となりましたが、「気をつけて帰ってね」、「さようなら」など笑顔で挨拶を交わしながらの取り組みとなりました。
ご参加いただいた保護者の皆様ありがとうございました。
つゝじヶ丘同窓会奨学金授与式が行われました
7月17日(水)、校長室にてつゝじヶ丘同窓会奨学金授与式が行われました。
つゝじヶ丘同窓会奨学金は、西高生の充実した学校生活を送ってもらうために、公立高女第26期生有志一同のご厚意を元に設立されたものです。
授与式では、つゝじヶ丘同窓会長から、18名の生徒一人ひとりに奨学金が授与されました。また、同窓会長から奨学金の歴史と西高の伝統についてお話をいただき、代表生徒からお礼の言葉を述べました。
「つゝじヶ丘同窓会」のみなさま、西高生へのご支援に改めて感謝申し上げます。


つゝじヶ丘祭2025 3日目
7月5日(土)、つゝじヶ丘祭3日目は一般公開をいたしました。保護者や地域にお住まいの1,310 名の方々にご来校いただきました。校内では、各クラスのアミューズメント、模擬店、有志発表、部局同好会展示(茶道部・文芸部・美術部・競技かるた部・図書局・写真部・ボードゲーム同好会・はこにしクリエーション同好会)、探究成果発表が行われ、賑わいをみせました。閉祭式では、各部門の結果発表が行われ後、行事実行委員長からの挨拶で幕を閉じました。また、学校評議員会も行われ、4名の学校評議員に本校の取組状況を説明し、学校祭見学後に、様々ご意見をいただきました。
3日間の学校祭を無事終えることができました。ご協力を頂きました皆様に感謝申し上げます。




つゝじヶ丘祭2025 1日目
つゝじヶ丘祭2025が「今日青春しにきました」をテーマに本日スタートしました。
1日目は、全校生徒が函館市民会館大ホールに集まり、開祭式、合唱コンクール、吹奏楽局発表、ショートムービー発表を行いました。行事実行委員長からの元気な挨拶でスタートし、花松校長先生と生徒会長から挨拶がありました。全校生徒で校歌を斉唱した後、各クラスで決めた自由曲の合唱で18クラスが競いました。また、吹奏楽局は、5曲を披露してくれました。会場には、約450名の保護者の皆様に観覧していただき、1日目を終えました。
明日4日(金)は15時30分から西部地区で仮装パレード、5日(土)は10時から13時40分まで一般公開を予定しています。








「街ガチャin函館」を公表しました
本校探究活動をしている3年次生2名がデザインを立案し、校内の約100名を対象にアンケートを行って、創立130周年を迎える函館商工会議所へ提案したものです。デザインは、カプセル販売を行う「funbox」の登録商標で、10種類(函館山ロープウェイ・函館市電・函館市長・五稜郭・やきとり弁当・イカの塩辛等)のアクリル製キーホルダーとなります。27日から1個300円で校内の他に、JR函館駅や五稜郭タワー、函館山麓駅など市内9ヵ所で二次元コードによる決済のみで販売します。
6月23日(金)NHK函館放送局で報道されました(映像はこちらからご覧になれます)※NHK函館放送局から許諾済

Linkリスト
-
北海道教育委員会 143
-
北海道函館西高等学校 - Wikipedia 528
-
つゝじヶ丘同窓会 29
-
つゝじヶ丘同窓会関西支部 62
-
つゝじヶ丘同窓会東京支部 347
-
つゝじヶ丘同窓会札幌支部 315
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |